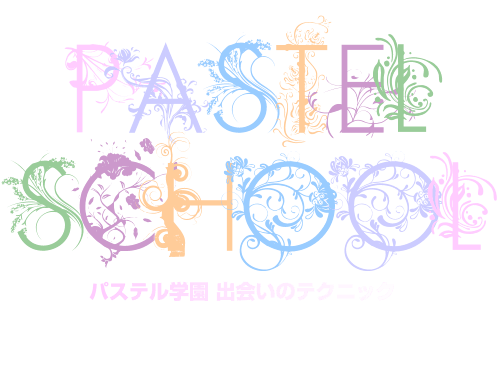とあるSM掲示板でM女を募集したところ、49歳の人妻からメールが来た。
年齢から、さぞかしベテランのM女かと思ったら未経験だと言う。
今まで浮気の経験もなく、真面目な主婦として生活してきたが、ネットを見ているうちにSMに惹かれるようになり、思い切ってメールをくれたらしい。
肉体的な快楽よりも精神的に支配されたいという願望を切々と綴ってくる。
丁寧な文章と言葉遣いから、教養のある女性であることも想像できた。
頻繁なメールのやり取りを1週間ほど続け、私に対する警戒感も徐々に解けてきたので、リアルでの面会をすることにした。
板橋区内のとある私鉄駅前に迎えに行く。
現れたのは、さすがに年齢は隠せない容貌だが、165cm、48kgというスレンダーな体型の女性だった。
想像した通り、知的な雰囲気を漂わせている。
これから初めて会った男とSMを愉しむなど、誰にも思えない女性だ。
私が指定した通り、薄手のブラウス、ミニスカート、ニーハイストッキングを身に着けており、細身の熟女の色気が漂う。
助手席に座ったが、極度の緊張感からか無言で俯いている。
初対面の挨拶をして握手を求めると、おずおずと右手を差し出してくる。
その手を優しく握り、そのまま両手で挟んでゆっくり撫でながら他愛のない話をする。
少しずつ強張っていた彼女の顔にも笑顔が見られるようになり、緊張も緩んできた頃。
「約束通り、してきた?」
聞くと、「はい・・・」と、恥ずかしそうに頷く。
この日、彼女に指示していたのは、先ほどの服装とノーブラで来ること、そして私は匂いフェチでもあるので、前日から風呂に入らず、トイレでもウォシュレットを使わないことも約束させていた。
「では、確かめるよ」
そう言ってブラウスのボタンを外して中に手を入れる。
小振りな乳房と、少し大きめの乳首を確かめる。
覚悟してきたのか、抵抗する素振りもなく目を瞑って俯く彼女。
「ちゃんと約束を守ったね、偉いよ」
そう言うと、俯きながら頷いている。
褒められたのが嬉しそうだ。
「もうひとつの約束も守ってる?」
「はい」
「では、確かめるので下着を脱いで」
「え?ここでですか?」
怯えたような表情で私を見る。
「うん、すぐに脱いで」
「はい・・・、わかりました」
少し躊躇していたが、スカートの裾から手を入れてショーツに手を掛ける彼女。
耳元まで赤くなっている。
「脱ぎました」
そう言ってショーツをバッグに仕舞おうとする。
私は手のひらを差し出す。
「見せなさい」
一瞬、首を振って拒否しかけたが、「はい・・・」と言って私の手に置いた。
黒いショーツだ。
彼女に見せつけるように広げ、じっくりと見る。
クロッチ部分を広げる。
白い液体が光っている。
肛門の部分がわずかに変色している。
指で液体に触れるとかなり粘っこく、全体が湿っている。
彼女は恥ずかしそうに、しかし私の指を凝視している。
鼻を近づけて嗅ぐ。
尿と酸性を思わせる液体の匂い。
変色した部分は明らかに便臭がする。
「かなり濡れているね?」
「ああ・・・」
「おしっこと、まんこの汁、それにうんこの匂いがはっきりわかるね、臭いよ」
「あああ、・・・やめて・・・」
消え入りそうな声で恥じらう彼女。
「ほら、自分の匂いだ、嗅ぎなさい」
「できません」
差し出したショーツから顔を遠ざけながら言う。
「命令です、嗅ぎなさい」
そう言うと、ようやく下着を受け取り、しばらく目を瞑っていたが。
「嗅ぎます」
クロッチの匂いを嗅ぎだした。
最初は小さく息を吸っていたが、だんだん私にもわかるくらい大きく匂いを吸い込み始めた。
「臭い?」
「はい、ああ臭いです、臭いです」
そう言ってますます匂いを嗅ぐ彼女。
その姿に私も興奮してくる。
「どんな匂いですか?」
「はい、私のおしっこの匂いがします」
「それだけですか?」
「はい、おまんこのやらしい匂いもします」
「舐めなさい」
「はい」
彼女は、人が歩いている駅前の道路に停めた車の中で、自分がさっきまで穿いていた下着の匂いに興奮し、躊躇うことなく自分の汚れに舌を伸ばし、舐め始めた。
私は完全に勃起していた。
「どんな味ですか?」
「しょっぱくて、臭い味です、ああ・・・臭いです・・・私、臭いです・・・」
ショーツの匂いを嗅ぎながら舐める姿は変態女好きな私の理想である。
右手を伸ばし、ミニへ手を入れようとすると、彼女は何も言っていないのに足を大きく広げる。
スカートを捲り上げて触る。
薄い陰毛から割れ目が見えている。
触れると、かなり大きいクリトリスが硬く尖っており、その下のラビアはぱっくり口を開け、ヌルヌルした液が溢れていた。
「あああ・・・気持ちいいです・・・」
車の外へ聞こえるのではないかと思うくらいに大きな声で切なそうに声を上げる彼女。
すでに彼女は、ただのメスに変貌していた。